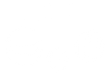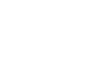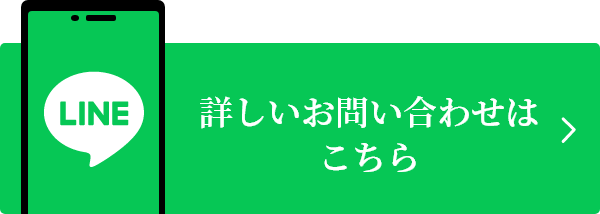梶原 靖元Yasumoto Kajihara
-
ギャラリー一番館
からのご紹介 - 陶歴・プロフィール
-
現在の唐津において、古唐津の復元にもっとも精力を傾けているのが梶原氏だと言われています。元来は粘土とされる古唐津の原料に砂岩を用い、十年の歳月をかけて「古唐津そのもの」と専門家に評されるほどの唐津を作陶されています。
2001年以来、古唐津のルーツを求め韓国の古窯を数多く訪れその研究活動にも余念はありません。唐津焼において学術的な知識にも長けた作家で、長い間研究しており、砂岩の地層や唐津の分布など、論理的かつ化学的な側面にも精通しています。特に焼成反応についての理解が深く、温度や時間によって色がどのように変わるかなど、理論的な知識を持ち作陶されています。修業と挑戦の歴史
梶原氏は唐津焼窯元で6年の修業の後、デザイン性のあるクラフト作品をめざし京都に向かい、その10年は様々なことを試し自分の理想の形を模索し現在の礎となりました。その後、氏は唐津に戻り本格的な古唐津の再現に取り掛かるようになります。佐賀県東松浦郡北波多村大字帆柱字鮎帰の古窯、飯洞甕窯の近くに窯を構え、器を作る材料はすべてその付近で採れるものを使用。飯洞甕窯は、歴史上初めて唐津に現れた最古の登窯です。
独自の素材と技法
素材感が他の唐津焼作家と明らかに異なる梶原氏は、まずほとんどの工程を古唐津を作っていた陶工達に近づけるため、窯の場所の地理やその時代の焼き物の制作条件を研究し、限られた素材・限られた条件のもと、作陶し続けています。素材は砂岩の塊を石臼で引き、細かい物だけを使う。釉薬は窯付近の草や藁が材料で、鉄絵に使う鬼板もこの付近のものです。窯は耐火煉瓦ではなく昔ながらの粘土で作っているので、窯の温度が1250度を超えると窯自体が壊れます。したがって、昔の陶工と同じく、低温かつ短時間で焼成をし、水簸され、絶妙な配分で挽かれた砂岩により漏れを防ぐのです。
梶原靖元氏は61歳で、唐津焼において学術的な知識にも長けた存在です。梶原氏は長い間研究しており、砂岩の地層や唐津の分布など、論理的かつ化学的な側面にも精通しています。特に焼成反応についての理解が深く、温度や時間によって色がどのように変わるかなど、理論的な知識を持つことが彼の特徴です。
このベースとなる素材作りは多くの唐津の作家が試していますが、現在の梶原氏のようにはなかなかできないと度々話を聞きます。その日の天候、砂岩の状態、釉薬とのバランスなど長年培ってきた氏の知識と経験が、梶原氏でしか作り出せない古唐津を可能にしているのです。枯唐津と新たな挑戦
近年では、「枯唐津」と命名された作品を発表しており、これは、今まで古唐津で使用されてきた素材とは異なる素材、砂岩を用い当時の製法をもって作られた器達です。いわゆる新唐津の誕生ともいえる器で、梶原氏らしい唐津ファンの心を掴むユニークな作品達です。様々な手法を用い、しかし一貫した古唐津への氏の解釈は多くの人から支持され、現在ではもっとも注目される唐津の作家の一人となりました。



展示会や作家仲間との活動
梶原靖元氏は、約10年前に制作した茶碗が、奥高麗の風合いに近いとして高い評価を受けました。この茶碗は、福岡ギャラリーでの展覧会で初めて見られ、その美しさは今もなお印象的です。それは一番館店主も、梶原氏の作品ほど古唐津に近いものは見当たらないと語るほど。氏の展覧会が開かれるたびに様々な陶芸家も訪れ、その高い完成度の焼き物に感銘を受けています。
氏は奥高麗の茶碗に近い作品を制作するだけでなく、韓国の焼き物にも強い興味を持っています。2023年には、氏が先導し、岡本作礼・矢野直人等の唐津焼作家とともに韓国の京流山での制作活動に参加し、古い土を使用して昔風の韓国の焼き物を焼きました。古唐津だけでなく、朝鮮で焼かれた古い焼き物にも深い関心を寄せています。 -
【プロフィール】
生年 1962年
窯元 大谷陶房 飯洞甕窯
趣味 お酒
【陶歴】
1962 佐賀県伊万里市に生まれる
1980 有田工業高等学校 デザイン科卒
1986 唐津焼窯元 太閤三ノ丸窯に弟子入
1989 大丸北峰氏に師事し煎茶道具を習う
1994 朝日現代クラフト 入選
1995 現代茶陶展 入選
1995 唐津市 和多田にて独立する
1996 淡交社 茶道美術展「鬼子」入選
1997 佐里 大谷に穴窯築窯
2003 第100回 九州山口陶磁展 経済産業大臣賞受賞
2003 韓国にて海外研修
2004 韓国「古唐津のルーツを求めて」古窯跡視察 「古唐津研究会発足」
2005 中国の地質巡検
2005 NHK BS2「侘びの茶碗をよみがえらせたい」放映
2007 陶芸散歩の会 会員展出品
2007 NHK教育 「美の壺」出演
2011 GALLERY一番館にて個展